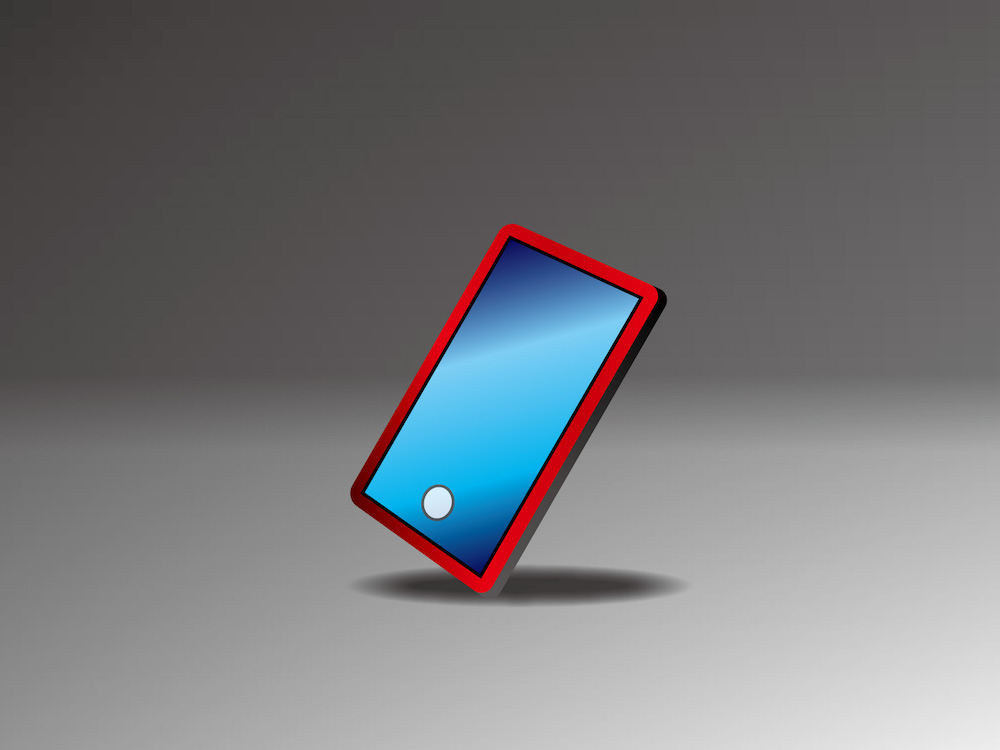1,雇用契約上の指示業務を行う
日本では労働者不足が顕著になった頃から、正規雇用ではなく非正規雇用の派遣社員を就業させて労働者不足の解消を担っていました。
これは正規雇用者の場合は直接雇用になるため採用活動は就業先が行うことになり、その手間と共に欲しい人材を集めるのに限界があり、派遣業者を活用すればもっと広い立場で求職者を集めることが可能になり、採用に関する手間も大幅に軽減できるという利点があるからです。
ところが現在では非正規雇用である派遣社員は産業構造の中で繁忙期に雇用し、閑散期になれば契約更新をせずに人数の調整を行いやすいという理由で雇用されるようになっていきます。
▶️参考:派遣事務渋谷区の給料などお仕事情報
これは以前の派遣業法では適正に更新手続きを行えば本人の意思に関係なく更新をしないことができたからですが、これは派遣で働く人にとっては雇用の不安定さと共に不満を持つ場合が多く、現在では契約更新をしない理由に制限が加えられるようになっていて、簡単には雇い止めができなくなりました。
このような理由から派遣社員であっても一定の雇用に対する安定性が持たれるようにはなってきましたが、その業務内容は正規雇用者と異なっているのは現在も継続されています。
派遣事務というのは正規雇用者ではない非正規雇用で雇われている人が事務職を行っていることになり、その業務についてはほとんどのケースで正規雇用者が行うものとの違いはありません。
この業務内容については雇用形態に関係なく、同じ仕事を行う場合がほとんどであり、その大きな違いは派遣雇用されている人は責任に対する割合が低くなっているということです。
つまり、派遣雇用されている場合には責任者からの指示を受けて業務を行うことになり、その意味合いは補助となります。
このような理由から派遣で業務を行っている人は、責任ある役職に就くことはありません。
これが直接に企業が雇用した人と、間接的に雇用された人との違いになるでしょう。
つまり派遣事務というのは、責任者から指示を受けて事務作業に従事することになり、これは正規雇用されている人とほとんど同じになっています。
2,現在は正規雇用者と同じような業務を行っている
派遣法では複数の仕事で業務を兼務することが禁止されていて、事務職の場合には最初に規定された場所での業務しか行えません。
これが正規雇用者であれば、企業の事情で別の部署において従前の業務とは異なった仕事を行ってもらうことが可能になっています。
そのため、派遣労働者は最初に就業した職場から基本的に異動することはなく、同じ業務を行うことになります。
派遣事務の業務は派遣された企業の考え方で扱う内容が異なりますが、原則的に責任ある仕事は任せない傾向が強くなっています。
事務というのは会社を運営する際の書類上の処理を行うことになりますが、当然に金銭に関する書類についても対応する場合があります。
この金銭については労働者の給与だけでなく、取引先との業務による支払いや領収もあるでしょう。
扱う金額も高額になり信用と責任の重さも高くなっているので、このような会社にとって極めて重要な事務については正規雇用者に任す場合が多くなっています。
このような理由から派遣事務で雇用されると待遇や給与以外にも、仕事内容についても差異が生じることがあるでしょう。
非正規雇用になる派遣労働者ですが、その法律が改訂されたことで正規雇用者との格差が低くなっています。
最も顕著なのが給与であり、昇給や賞与などは別にして、基本給については正規雇用者と変わらなくなっています。
3,派遣事務をきっかけに正規雇用の道も
また以前にもあった同一事業所で三年間就業すれば直接雇用するか契約更新をしないという規定が、直接雇用することを重視するようになっていて、大企業を中心に正規雇用される確率が高くなっていると言えるでしょう。
この場合の雇用形態は正社員である必要がないので、契約や準社員などの場合もあります。
これは昇級に関係することになりますが、直接雇用されることで雇用の安定は飛躍的に高くなり、働く人の就業意欲を増してくれることは間違いありません。
三年間経てば別の仕事先を探さなければいけないのではという不安が低減したことは、非正規雇用で働く人に仕事に対する意欲を増加してくれるのは企業にとってもメリットがあります。
派遣事務であっても就業先企業に認めてもらえば短期間で直接雇用に切り替えてもらえるチャンスがあり、業務内容もより正規雇用者に近いものになる可能性は少なくないでしょう。
人間には事情があって直接雇用されていない人が多くいますが、本人のやる気や能力があるのであれば、企業もその人が希望する方法を提供してあげるべきです。
派遣についての状況は確実に改善しているので、これからも採用方法が異なるだけで差を設けないようにするための努力が必要になってくるでしょう。